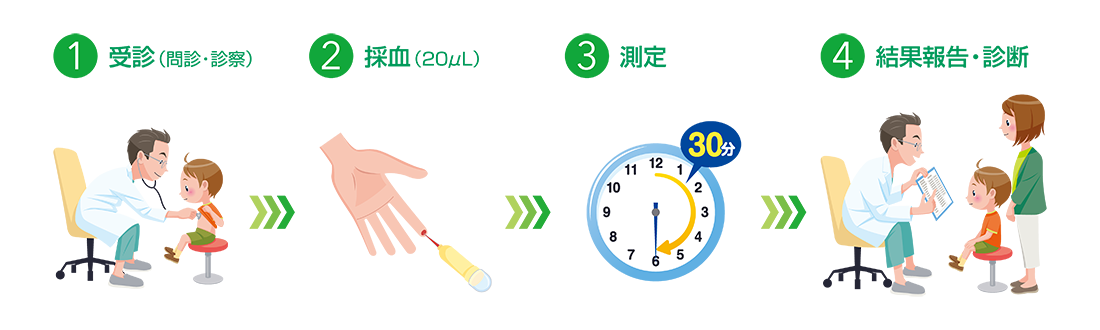アレルギー皮膚科の対象となる主な疾患
- アトピー性皮膚炎
- かぶれ(接触性皮膚炎 せっしょくせいひふえん)
- 手湿疹
- じんましん
- 食物アレルギー
- アナフィラキシー
- 薬物アレルギー(薬疹 やくしん)
- 花粉症(花粉症皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎)
アトピー性皮膚炎
小さなお子様から、忙しく働いている方まで、悩まれている方が多い病気です。
原因としては、皮膚のバリア機能の低下、アトピー素因(アレルギー体質)、心理的要因の3つが重なって起きると考えられています。
アトピー性皮膚炎は、「良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら、慢性に経過するかゆみを伴う湿疹」と定義されています。当院では、日本皮膚科学会が作成しているガイドラインに沿った適切な治療を行います。治療は、「皮膚のバリア機能を補うために保湿剤を使用」し、「悪化させる因子を除き」、「信頼できる医院で長く通院して薬物療法を行う」ことが3つの柱となります。
当院では、保湿剤の徹底と、重症度に応じて皮膚の炎症やかゆみを抑えるためのステロイド、タクロリムス、JAK阻害薬、PDE4阻害剤の外用を使用し、アレルギー反応やかゆみを軽減させる抗アレルギー剤の内服を併用させています。また難治性の方には生物学的製剤(デュピクセントなど)やJAK阻害薬内服も必要に応じて組み合わせています。アトピー性皮膚炎は良くなったり、悪くなったりを繰り返すがゆえに、いわゆる“ドクターショッピング”をしがちな皮膚疾患です。いい時も悪い時も知っている、信頼できる医院でのしっかりした治療を継続することが大事です。
かぶれ(接触性皮膚炎 せっしょくせいひふえん)
接触性皮膚炎とは、原因になる物質が皮膚に接触し、それが刺激やアレルギー反応となってかゆみを伴う皮疹があらわれます。一般には「かぶれ」とも呼ばれますが、接触した部分に紅斑(あかみ)があらわれて小水疱(水ぶくれ)を生じる場合があります。また化粧品なら顔面、ピアスなら耳、歯科金属なら歯茎や口唇、シャンプーなら頭皮や手のひらなど、多くの皮膚炎は原因となる物質が接触する場所に生じます。そのため接触性皮膚炎を疑う場合は、皮疹があらわれる部位に関連した生活用品などを調べます。
確実に診断するためには、「パッチテスト」で疑わしい物質を貼付して48時間後に皮膚反応を確認します。金属アレルギーの場合は1週間後に陽性反応があらわれるなど、診断に時間がかかる場合があります。接触性皮膚炎の原因がわからないままだと、予防の対策がたてられないだけでなく、重症化してしまうこともあります。問診によって意外な原因が判明することもあります。重症例では潰瘍を伴うこともありますので、早めに皮膚科専門医に相談してください。
手湿疹
手湿疹はいわゆる「手あれ」がさらに進行した状態と考えられており、皮膚の赤みやかゆみ、小さなブツブツなど、いくつかの症状が混ざりあって発症します。皮膚を外的刺激から守る「皮膚のバリア機能」が低下しているため、洗剤や薬剤がしみて、ピリピリとした痛みを感じることもあります。さらに悪化すると、皮膚が極度に乾燥して亀裂やひび割れを生じるタイプと、ブツブツや水疱ができるなどして患部がジュクジュクとするタイプのどちらかの手湿疹に進行します。重症化すると患部が化膿することもあるため注意が必要です。
刺激性皮膚炎
洗剤や化粧品、薬品、食べ物、植物に含まれる刺激性物質に触れることによって手指の皮膚がダメージを受けて発症する皮膚炎です。手湿疹の7割がこの刺激性皮膚炎だといわれており、原因となる物質に触れる頻度の高い利き手の指先を中心に症状が出やすいのが特徴です。水仕事や乾燥、アトピー性皮膚炎などによって皮膚のバリア機能が低下しているとより発症しやすくなります。
化学物質によるアレルギー接触性皮膚炎
化学物質に対するアレルギー反応によっておこる皮膚炎です。洗剤や化粧品、薬品、植物などに含まれる特定のゴム製品の成分、金属に対して免疫が働き、アレルギー反応を起こす体質になることを「感作(かんさ)」といいます。一度、特定の物質に対する感作が起きると、再び同じ物質に触れることでアレルギー反応を生じ、かぶれを発症します。アレルギー反応によって、かゆみ物質であるヒスタミンなどが皮内に放出されるため、湿疹やかゆみの症状が強い傾向にあります。治療としては接触源を除くことが基本です。薬物療法としてステロイド外用、抗アレルギー剤内服を行いますが、重症例には一時的にステロイド内服をして頂くこともあります。
じんましん
典型的なじんましんは、蚊に刺されたような膨疹がでます。「かゆみを伴う盛り上がった赤い皮疹」ができて、数時間以内に消える症状が現れます。急激に全身にでてしまうと体が熱をもつような感じがしたり、かゆくて眠れなくなったり、仕事や勉強に集中できないこともあります。治療は、飲み薬(抗アレルギー薬)が中心で、塗り薬は補助的に使用する程度です。抗アレルギー剤は、じんましんにとてもよく効くと言われています。しかし、1種類の薬では効果が得られない場合もあり、数種類の薬を併用したり、注射製剤を使用する場合もあります。慢性的なじんましんは途中で薬をやめてしまうと再燃するため、根気よく自分にあった内服薬を続けることが重要です。ご相談ください。
食物アレルギー
今麦やそば、甲殻類など特定の食べ物を食べた後に、蕁麻疹や喘息症状が出る疾患です。治療は原因となる食物の除去ですが、お子様の場合は成長につれて食べられるようになることがあります。蕁麻疹に準じた治療を行いますが、症状が強い際にはステロイド内服・注射、場合によってはアドレナリンの注射が必要です。
アナフィラキシー
食べ物や薬・虫刺されなどを原因とするⅠ型アレルギー反応により、肥満細胞からヒスタミンが放出され好酸球の遊走を伴う炎症を起こします。それにより、急激な痒み・嘔吐・下痢などが引き起こされ、重篤な場合には血管の拡張による血圧低下(アナフィラキシーショック)が起こります。適切な対応が必要ですが、アナフィラキシーの既往がある方には、当院でエピペン(アドレナリン自己注射薬)の処方を行っております。
薬物アレルギー(薬疹)
接種した薬剤に起因する発疹を薬疹と呼びます。被疑薬を中止することが重要ですので、病歴の詳細な聴取を致します。抗ヒスタミン薬、ステロイド外用による治療が一般的ですが、重症になるとステロイド内服や注射が必要になります。疑わしい薬剤については、DLST(drug-induced lymphocytes stimulation test)といった採血検査が被疑薬の同定に役立ちます。
花粉症(花粉症皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎)
花粉に起因する皮膚の腫れ・痒みや、鼻炎症状、目の痒み・充血などを指します。原因となる花粉が飛散する時期に限り症状が出現し、その他の季節は無症状であることが多いです。症状により、抗ヒスタミン薬の内服、ステロイド内服・外用を行います。