2025年9月25日

皮膚科で処方される薬の保険適用の基本
皮膚科を受診すると、症状に応じてさまざまな薬が処方されます。湿疹やアトピー性皮膚炎、にきび、水虫など、皮膚の悩みは多岐にわたります。これらの治療薬は保険適用されるものが多いですが、すべての薬が保険でカバーされるわけではありません。
皮膚科で処方される薬の保険適用について正しく理解することは、患者さんの経済的負担を軽減するだけでなく、適切な治療を継続するためにも重要です。保険診療と自由診療の違いや、保険適用の条件について知識を持っておくことで、皮膚の健康管理をより効果的に行うことができるでしょう。
保険診療として診療報酬が支払われるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。皮膚科専門医が保険医療機関において、健康保険法や医師法などの関係法令を遵守し、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に従って、療養上妥当適切な診療を行うことが求められます。
では、具体的にどのような薬が保険適用となり、どのような場合に自己負担が増えるのでしょうか。皮膚科診療における保険適用の基本的な考え方を見ていきましょう。
保険適用される皮膚科の薬剤
皮膚科で処方される薬剤のうち、保険適用されるものは多岐にわたります。一般的な皮膚疾患の治療に使用される薬剤は、基本的に保険診療の対象となります。
アトピー性皮膚炎の治療に使用されるステロイド外用薬や免疫抑制外用薬(タクロリムス軟膏など)、抗ヒスタミン薬は保険適用されます。また、2023年には重症円形脱毛症に対するJAK阻害薬(バリシチニブやリトレシチニブ)も保険適用となりました。これらの薬剤は皮膚科専門医の診断と処方に基づいて使用することで、保険診療の対象となります。
皮膚感染症の治療に使用される抗菌薬や抗真菌薬、抗ウイルス薬も保険適用されます。水虫(白癬)の治療薬、とびひ(伝染性膿痂疹)の治療薬、帯状疱疹の治療薬なども保険診療の範囲内です。
乾癬の治療に使用される生物学的製剤(分子標的薬)も、適切な診断と重症度評価に基づいて処方される場合は保険適用となります。ただし、これらの薬剤は高額であるため、高額療養費制度を利用することで患者負担を軽減することができます。
皮膚科で行われる処置や手術も、医学的に必要と判断される場合は保険適用されます。例えば、いぼの冷凍凝固処置や皮膚腫瘍の摘出術などが該当します。ただし、これらの処置も部位や範囲によって保険点数が異なるため、診療録への適切な記載が重要です。
どう思いますか?皮膚の症状で悩んでいても、適切な診断を受ければ保険適用で治療できることが多いのです。

保険適用外となる皮膚科治療
一方で、皮膚科で行われるすべての治療が保険適用になるわけではありません。美容目的の治療や、保険診療の対象外とされている薬剤・処置もあります。
美容皮膚科で行われるしみ・そばかす・肝斑の治療、しわ・たるみの改善、ニキビ跡の治療、医療脱毛などは基本的に保険適用外です。これらは「美容目的」と判断され、自由診療(自費診療)となります。また、ボトックス注射やヒアルロン酸注入などの美容医療も保険適用外です。
AGA(男性型脱毛症)の治療も基本的に保険適用外です。フィナステリドやデュタステリド、ミノキシジル外用薬などのAGA治療薬は、「美容的な問題」と分類されるため、原則として保険が適用されません。ただし、円形脱毛症の治療は自己免疫疾患とされるため、ステロイド剤や免疫抑制剤の投与が保険適用となります。
また、市販薬と同等の成分・用量の医療用医薬品(OTC類似薬)についても、保険給付の見直しが検討されています。2025年末までの予算編成過程で十分な検討が行われ、早期に実現可能なものについては2026年度から実施される可能性があります。これにより、一部の皮膚科で処方される薬剤が保険適用外となる可能性があります。
保険適用外となる治療を受ける場合は、事前に費用について確認しておくことが重要です。医療機関によって料金設定が異なるため、複数の医療機関で相談することも一つの方法です。また、医療費控除の対象となるかどうかも確認しておくと良いでしょう。
保険適用の条件と注意点
皮膚科で処方される薬が保険適用されるためには、いくつかの条件があります。まず、保険医療機関において保険医が診療を行うことが前提です。また、処方される薬剤が保険適用の対象であること、そして適切な診断と処方が行われることが必要です。
皮膚科の診療では、診療録(カルテ)への適切な記載が非常に重要です。診療の都度、医学的に妥当適切な傷病名を診療録に記載する必要があります。慢性・急性の区別、部位、範囲(大きさ)、左・右の区別を必ず記載することが求められます。特に皮膚科軟膏処置、熱傷処置、いぼ等冷凍凝固処置では、皮疹の部位及び範囲によりレセプト上の点数に差があるため、記載が不十分だと最小範囲とみなされ、査定や減点の対象となることがあります。
また、「疑い病名」での処方や検査にも注意が必要です。疑いだけの場合は処方した薬剤が査定されたり、検査が返戻・査定されたりすることがあります。診断がついた時点で確定病名に変更する必要があります。
保険適用の薬剤であっても、適応外使用の場合は保険適用外となることがあります。例えば、保湿薬は皮膚の乾燥を伴う疾患に適応がありますが、乾燥症状が考えられない疾患に使用した場合は査定対象となります。「湿疹」や「接触皮膚炎」「アレルギー性皮膚炎」などの病名では認められないことがあります。
また、いわゆる「レセプト病名」(保険請求のためだけに用いられる架空の傷病名)を用いることは不適切な請求とみなされます。保険適用であっても、一連ないし初診時のみ請求できるものに対し部位・病名を変えて請求することも、査定逃れのために意図的に毎回異なる疾患名や部位を記載することも不適切です。
これらの条件や注意点を理解し、適切な診療と処方を受けることで、必要な治療を保険適用で受けることができます。不明な点があれば、担当医に相談することをお勧めします。
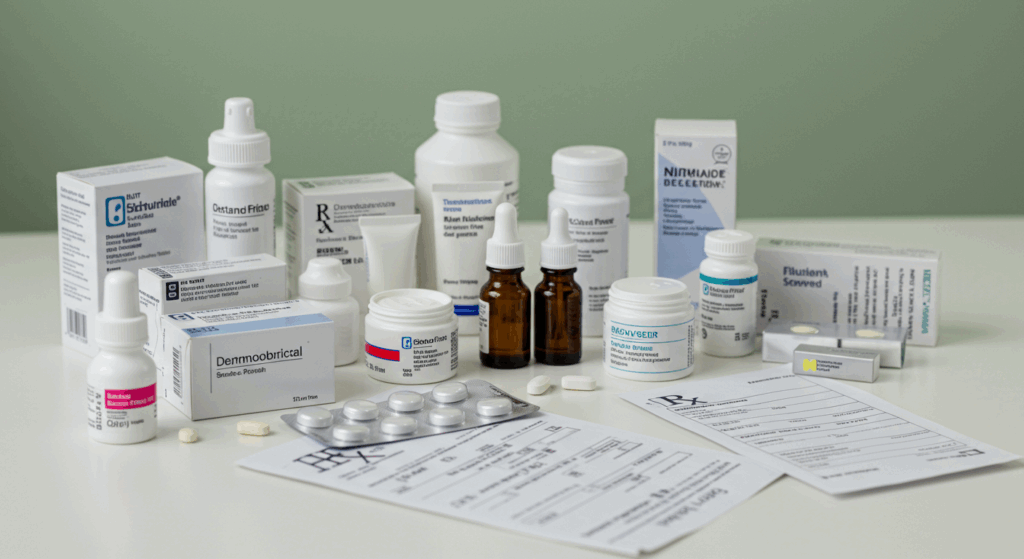
特殊な皮膚疾患の保険適用
皮膚科では、一般的な皮膚疾患だけでなく、特殊な皮膚疾患の治療も行われています。これらの疾患に対する治療薬の保険適用状況について見ていきましょう。
アトピー性皮膚炎の治療では、従来のステロイド外用薬や免疫抑制外用薬に加えて、近年では生物学的製剤(デュピルマブ)やJAK阻害薬(バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブ)なども保険適用となっています。ただし、これらの薬剤は一定の条件を満たす必要があります。JAK阻害薬の使用には、皮膚科専門医が常勤していること、乾癬分子標的薬安全対策講習会の受講履歴があること、薬剤の導入および維持において近隣の施設に必要な検査をお願いできることなどの要件があります。
乾癬の治療では、従来の外用薬や光線療法に加えて、生物学的製剤(TNFα阻害薬、IL-17阻害薬、IL-23阻害薬など)も保険適用となっています。これらの薬剤は高額ですが、重症例では保険適用となり、高額療養費制度を利用することで患者負担を軽減できます。
円形脱毛症の治療では、2022年にJAK1/2阻害薬(バリシチニブ)が、2023年にはJAK3/TECファミリーキナーゼ阻害薬(リトレシチニブ)が重症円形脱毛症に保険適用となりました。これらの薬剤の使用には、正しい診断、適切な重症度判定、病態の把握、さらには安全性の担保が必要です。
皮膚悪性腫瘍(メラノーマなど)の治療では、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬などの薬物療法も保険適用となっています。これらの治療は、適切な診断と病期分類に基づいて行われる必要があります。
皮膚T細胞性リンパ腫の治療も、進行期には化学療法や分子標的薬などが保険適用となります。これらの治療は専門的な知識と経験を持つ医師のもとで行われることが重要です。
これらの特殊な皮膚疾患の治療では、専門的な医療機関での診療が推奨されます。大学病院や専門病院では、最新の治療法や臨床試験なども行われており、より適切な治療を受けられる可能性があります。また、これらの疾患では長期的な治療が必要となることが多いため、医療費の負担についても事前に相談しておくことが大切です。
保険適用外の薬剤と自己負担
保険適用外となる薬剤を処方された場合、その費用は全額自己負担となります。特に美容目的の治療や市販薬と同等の薬剤などは、保険適用外となることが多いです。
美容皮膚科で行われるしみ・そばかす・肝斑の治療、しわ・たるみの改善、ニキビ跡の治療、医療脱毛などは基本的に保険適用外です。これらの治療にかかる費用は医療機関によって異なりますが、一般的に高額になることが多いです。例えば、しみ治療のレーザー治療は1回あたり数千円から数万円、ボトックス注射は部位によって1万円から数万円、医療脱毛は部位や回数によって数万円から数十万円かかることがあります。
AGA(男性型脱毛症)の治療も基本的に保険適用外です。フィナステリドは月額4,000〜7,000円、デュタステリドは月額6,000〜10,000円、ミノキシジル外用薬は月額3,000〜8,000円程度かかります。自毛植毛は30〜200万円以上、注入療法(メソセラピー)は1回あたり2〜10万円程度かかることがあります。
また、2025年末までの予算編成過程で検討されているOTC類似薬(市販薬と同等の成分・用量の医療用医薬品)の保険給付見直しにより、一部の薬剤が保険適用外となる可能性があります。例えば、アレルギー性鼻炎の治療薬であるアレジオン錠20は現在約160円(24日分)ですが、市販薬のアレジオン20(24錠)は約2,000円です。同様に、去痰剤のムコダイン錠500mgは約70円(1週間分)ですが、市販薬のムコダイン去痰錠Pro500(20錠)は約2,500円です。保険給付から除外されると、患者負担が大幅に増える可能性があります。
保険適用外の治療を受ける際は、事前に費用について確認し、医療費控除の対象となるかどうかも確認しておくことが重要です。また、複数の医療機関で相談し、費用対効果を比較検討することも一つの方法です。
患者さんが知っておくべき保険制度の活用法
皮膚科での治療費を抑えるためには、保険制度を上手に活用することが重要です。ここでは、患者さんが知っておくべき保険制度の活用法について説明します。
まず、高額療養費制度を理解しておくことが大切です。この制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度です。特に生物学的製剤やJAK阻害薬などの高額な薬剤を使用する場合は、この制度を利用することで負担を軽減できます。事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが限度額までで済むため、一時的な負担も軽減されます。
次に、医療費控除を活用することも重要です。1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)を超えた場合、確定申告をすることで所得税が還付されます。皮膚科での治療費だけでなく、通院のための交通費や市販薬の購入費なども医療費控除の対象となる場合があります。ただし、美容目的の治療費は医療費控除の対象外となることが多いため注意が必要です。
また、自治体の医療費助成制度も活用できる場合があります。特に子どもの医療費助成制度は多くの自治体で実施されており、小児皮膚科での治療費が軽減される可能性があります。また、難病患者や障害者向けの医療費助成制度もあります。例えば、重症の乾癬や天疱瘡などは難病医療費助成制度の対象となる場合があります。
さらに、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択することで、薬剤費を抑えることができます。ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の有効成分を含み、効果も同等とされていますが、価格は3〜5割程度安くなることが多いです。皮膚科で処方される外用薬や内服薬にもジェネリック医薬品があるため、医師や薬剤師に相談してみるとよいでしょう。
これらの制度を上手に活用することで、皮膚科での治療費負担を軽減することができます。不明な点があれば、医療機関の窓口や保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)に相談することをお勧めします。

まとめ:皮膚科での薬剤選択と保険適用の考え方
皮膚科で処方される薬の保険適用について、重要なポイントをまとめてみましょう。まず、一般的な皮膚疾患の治療に使用される薬剤は、基本的に保険診療の対象となります。アトピー性皮膚炎、湿疹、皮膚感染症、乾癬などの治療薬は保険適用されることが多いです。
一方で、美容目的の治療や、保険診療の対象外とされている薬剤・処置は自己負担となります。美容皮膚科での治療やAGA治療は基本的に保険適用外です。また、市販薬と同等の成分・用量の医療用医薬品(OTC類似薬)についても、今後保険給付の見直しが行われる可能性があります。
保険適用されるためには、保険医療機関において保険医が診療を行い、適切な診断と処方が行われることが必要です。診療録への適切な記載も重要であり、傷病名や部位、範囲などを明確に記載する必要があります。
特殊な皮膚疾患の治療では、生物学的製剤やJAK阻害薬などの新しい治療薬も保険適用となっていますが、使用には一定の条件があります。これらの薬剤は高額であるため、高額療養費制度を利用することで患者負担を軽減できます。
患者さんは、高額療養費制度や医療費控除、自治体の医療費助成制度、ジェネリック医薬品の活用など、様々な方法で治療費負担を軽減することができます。不明な点があれば、医療機関の窓口や保険者に相談することをお勧めします。
皮膚の健康は生活の質に大きく影響します。適切な診断と治療を受け、必要な場合は保険制度を上手に活用して、皮膚の健康を維持していきましょう。皮膚のトラブルでお悩みの方は、ぜひ皮膚科専門医にご相談ください。
当院では、保険診療を主体に皮膚疾患の診療を行っています。アトピー性皮膚炎や乾癬などの慢性疾患から、湿疹やにきびなどの一般的な皮膚疾患まで、幅広く対応しています。保険適用についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
詳細は駒沢自由通り皮膚科のウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。皆様の皮膚の健康をサポートいたします。

監修:白石 英馨(しらいし ひでか)
駒沢自由通り皮膚科 院長・日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医
東京慈恵会医科大学医学部卒業後、同大学附属病院や関連病院にて皮膚科診療に従事。アトピー性皮膚炎やニキビといった一般皮膚疾患から、ホクロ・イボの外科的治療、美容皮膚科領域まで幅広く経験を積む。
2025年3月、世田谷・駒沢に「駒沢自由通り皮膚科」を開院。小さなお子さまからご高齢の方まで、地域に根ざした“かかりつけ皮膚科”として丁寧でわかりやすい診療を心がけている。
- 所属学会:日本皮膚科学会、日本美容皮膚科学会 ほか
- 専門分野:皮膚科一般、小児皮膚科、美容皮膚科、日帰り皮膚外科手術





